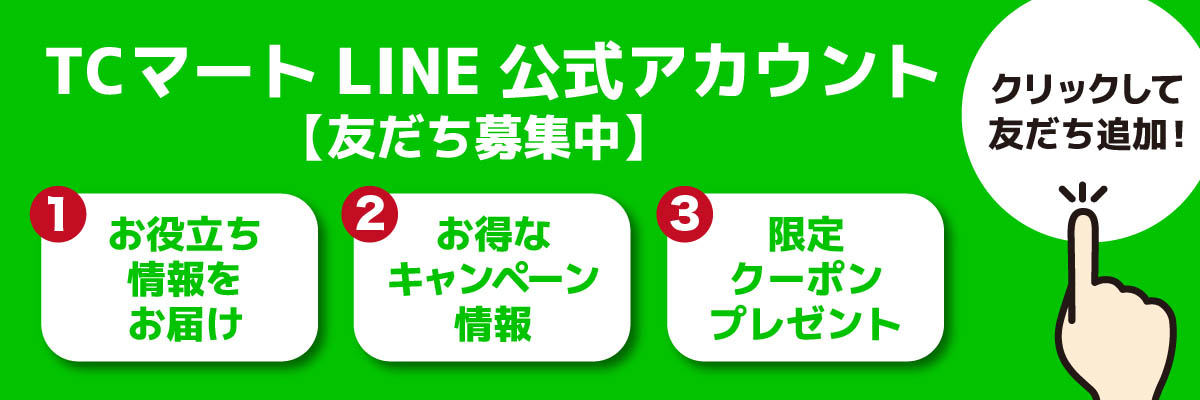これから高齢の親御さんと同居を始めるにあたり、身の回りの準備を進めているけれど、意外と悩むのが「服」のことではないでしょうか。「どんな服なら一人でも着替えやすい?」「季節ごとに何枚くらい用意すればいいの?」など、分からないことも多いですよね。
私の親も最近、少し身体の動きに不安が出てきたこともあり、服選びには本当に頭を悩ませました。そんな経験から言えるのは、高齢者の服の準備は、ただ数を揃えれば良いというものではない、ということです。
この記事では、まさに今、同じようなお悩みをお持ちのあなたのために、高齢の親御さんとの同居生活で必要になる服の準備について、失敗しないための具体的な進め方から、選び方の基本、季節ごとの枚数の目安まで、私の経験も交えながら網羅的に解説します。
親御さんの安全と、そして「自分らしさ」を大切にする笑顔のために、一緒に最適な一着を見つけていきましょう。
同居準備、まず何から?失敗しない服の準備4ステップ
いざ親御さんの服を準備しようと思っても、何から手をつければ良いか戸惑ってしまいますよね。まずは焦らず、以下の4つのステップで現状を把握することから始めましょう。
ステップ1:今ある服を確認する(タンスの中身拝見!)
まずは、親御さんが今どんな服を持っているのか、一緒に確認させてもらいましょう。「この服はよく着ているわね」「これは最近着ていないの?」など、会話をしながら進めるのがポイントです。
持っている服を把握することで、本当に必要なもの、買い足すべきものが明確になります。
・着ている服・着ていない服の仕分け
・傷みや汚れのチェック
・サイズが合っているかの確認
ステップ2:親御さんの好みや意見を聞く(主役は親御さんです)
新しい服を選ぶ上で最も大切なのは、親御さん本人の気持ちです。「どんな色が好き?」「こういうデザインはどう思う?」と、カタログやインターネットの画面を一緒に見ながら、好みをリサーチしましょう。
機能性ばかりを重視して、本人の好きではない服を揃えてしまっては、着る楽しみがなくなってしまいます。あくまで主役は親御さん、という視点を忘れないようにしたいですね。
ステップ3:身体の状態を正しく知る(安全のための観察)
「最近、腕が上がりにくそうだな」「ボタンを留めるのに時間がかかっているな」など、日常生活での親御さんの様子を注意深く観察しましょう。以下のような点は、特に着替えやすい服を選ぶ上で重要なヒントになります。
・腕や肩はスムーズに上がるか?
・指先に力は入るか?震えはないか?
・立ったり座ったりする動作は安定しているか?
・トイレの回数や、日中の活動量はどれくらいか?
ステップ4:収納スペースを確保する(見つけやすく、取り出しやすく)
新しい服を迎える前に、収納場所を整えることも大切です。どこに何があるか一目で分かり、親御さん自身が楽に取り出せるような工夫を考えましょう。
・目線の高さの引き出しを活用する
・滑りの良いハンガーを選ぶ
・季節外の服は別の場所に保管する
これらのステップを踏むことで、無駄なく、そして親御さんにとって本当に快適な服を準備することができます。
もう迷わない!高齢者の服選びで重視すべき4つの最重要ポイント
準備のステップが見えたところで、次は具体的な服選びの基準を見ていきましょう。私が特に重要だと感じたのは、以下の4つのポイントです。
【ポイント1】転倒や事故を防ぐ「安全性」
何よりも最優先したいのが安全性です。ちょっとしたことが、思わぬ事故につながる可能性があります。
・裾の長さ: 長すぎるズボンの裾は、自分で踏んでしまって転倒の原因になります。ジャストサイズか、少し短めを選びましょう。
・袖口のデザイン: ゆったりしすぎた袖口は、テーブルの上のものに引っかかったり、調理中に火が移ったりする危険も。すっきりとした筒袖や、ゴムでまくれるものが安心です。
・滑りにくい素材: 特に靴下は、フローリングの床で滑って転倒するケースが非常に多いです。裏に滑り止めがついているタイプが絶対におすすめです。
【ポイント2】本人も介護者も楽になる「着替えやすさ」
身体機能の変化に伴い、これまで当たり前にできていた着替えが負担になることがあります。「着替えが面倒だから…」と、一日中パジャマで過ごすようになってしまうのは、心身の健康にとっても良くありません。
・前開きの服: Tシャツのように頭からかぶるタイプより、シャツやカーディガンのように前が開くタイプの方が、腕の動きが小さく済み、格段に着替えやすくなります。
・ゆとりのあるデザイン: 肩周りや腕周りにゆとりのあるラグラン袖などは、腕を通しやすくおすすめです。
・着脱しやすい留め具: 小さなボタンは、指先の力が弱くなると非常に扱いづらくなります。後ほど詳しく解説しますが、マジックテープ®やスナップボタンなどを活用しましょう。
着替えやすい服
【ポイント3】気持ちも明るくなる「本人の好み・おしゃれ心」
「もう年だから…」と、おしゃれを諦めてしまうのはとても寂しいことです。好きな色や柄の服を着ることは、気持ちを前向きにし、QOL(生活の質)を高めてくれます。
「この服を着ていると、なんだか元気が出るわ」と母が嬉しそうに話してくれた時、機能性だけでなく、本人の「好き」を尊重することの大切さを改めて感じました。
デイサービスなどにお出かけする際の、少しおしゃれな外出着を一緒に選ぶのも、社会との繋がりを保つ上でとても良い刺激になります。
気分の上がるおしゃれな柄のお洋服
【ポイント4】毎日の負担を減らす「洗濯のしやすさ」
同居生活では、洗濯の量も増えます。デザインや機能性だけでなく、お手入れのしやすさも忘れずにチェックしましょう。
・洗濯表示の確認: 自宅の洗濯機で気軽に洗えるか、乾燥機は使えるかなどを確認します。
・乾きやすい素材: 綿とポリエステルの混紡素材などは、シワになりにくく乾きやすいのでおすすめです。
・汚れが目立ちにくい色・柄: 食べこぼしなどが気になる場合は、濃い色や柄物を選ぶというのも一つの手です。
洗濯しやすい乾燥機対応商品
【身体の状態別】プロが教える「本当に着替えやすい服」の選び方
「着替えやすさ」と一言で言っても、親御さんの身体の状態によって最適な服は変わります。ここでは、具体的なケース別に、より専門的な選び方のコツをご紹介します。
腕が上がりにくい・肩が痛む方へ
四十肩・五十肩の後遺症や関節の痛みで腕が上がりにくい方には、前開きで全開になるタイプの服が最適です。
・トップス: 前開きのシャツ、ブラウス、カーディガン。肩周りが楽なラグラン袖や、アームホール(袖ぐり)が広いデザインを選びましょう。
・ボトムス: ウエストが総ゴムのものが着脱しやすく、締め付けも少ないため快適です。
指先の力が弱い・震えがある方へ
リウマチや加齢で指先の細かい動きが難しくなってきた方には、ボタンの代わりに以下のような留め具がおすすめです。
・マジックテープ®(面ファスナー):
メリット: 軽い力で開け閉めできる。
デメリット: 洗濯時に他の衣類とくっつきやすい(洗濯ネット使用で対策)。
・大きめのスナップボタン:
メリット: パチッと留める感覚が分かりやすい。指でつまみやすい。
デメリット: 少し力が必要な場合もある。
・ファスナー:
メリット: 一度に開け閉めできる。
デメリット: 一番下を差し込む動作が難しい場合がある。リング状の引き手など、つまみやすい工夫があるものが良い。
車椅子を利用している方へ
座った姿勢が長い方は、お尻周りの縫い目が床ずれの原因になったり、背中側の丈が足りなくなったりすることがあります。
・トップス: 後ろ身頃が長めに作られているデザインだと、背中が出にくく安心です。
・ボトムス: ウエストゴムで、股上が深いズボンがおすすめです。座ったままでも着脱しやすいように、両脇がファスナーで開くタイプのズボンも販売されています。
片麻痺がある方へ
脳梗塞の後遺症などで片麻痺がある場合は、着替えの順番にコツがあります。「脱ぐときは健側(動く方)から、着るときは患側(麻痺のある方)から」という「脱健着患(だっけんちゃっかん)」が基本です。
この原則を本人と介助者が共有しておくだけで、着替えがぐっとスムーズになります。袖口が広く、伸縮性のある素材の服を選ぶと、さらに楽になります。
【季節別】高齢者の服の準備リスト(枚数の目安付き)
「具体的に、何を何枚くらい揃えればいいの?」という疑問にお答えして、季節ごとの準備リスト(目安)を作成しました。親御さんの活動量や洗濯の頻度に合わせて調整してください。
春夏
・肌着: 5~7枚(吸湿性・通気性の良い綿素材。前開きタイプが便利。)
・トップス: 4~6枚(半袖・七分袖のTシャツ、ポロシャツ、ブラウスなど。洗い替えを多めに。)
・ボトムス: 3~4本(ウエストゴムのズボンや、ゆったりしたパンツ。乾きやすい素材が◎。)
・羽織もの: 2~3枚(薄手のカーディガン、ベスト。冷房対策や朝晩の気温差に対応。)
・パジャマ: 2~3組(通気性の良いガーゼ素材や綿素材。寝汗をしっかり吸うもの。)
秋冬
・肌着: 5~7枚(保温性・保湿性に優れたもの。七分袖・長袖タイプ。)
・トップス: 4~6枚(長袖のポロシャツ、トレーナー、セーターなど。重ね着しやすいもの。)
・ボトムス: 3~4本(裏起毛など暖かい素材のズボン。厚手でも動きやすいストレッチ素材が◎。)
・羽織もの: 2~3枚(フリース素材のベストやカーディガン。室内での体温調節に必須。)
・アウター: 1~2枚(軽くて暖かいダウンジャケットやコート。着丈が長すぎないもの。)
・パジャマ: 2~3組(スムース素材やキルト素材など、保温性の高いもの。)
通年であると便利なもの
・靴下(滑り止め付き): 5~7足
・ベスト: 温度調節に非常に役立つアイテムです。
どこで買う?高齢者の服が探せる場所とスッキリ収納のコツ
最後に、いざ服を買いに行くとなった時のおすすめの場所と、購入後の収納についてお話しします。
おすすめの購入場所
・介護用品・シニア向け衣料の専門通販サイト: 品揃えが豊富で、機能性に特化した商品が見つかりやすいのが魅力です。サイズ展開も豊富で、口コミを参考にできるのも良い点です。
・大型スーパーや衣料品チェーン店: シニア向けのコーナーが設けられていることが多く、実際に手に取って素材感やサイズを確かめられます。親御さんと一緒に買い物に行くのも楽しいですね。
シニア専門通販サイト TCマートのご紹介
「どこで探せばいいか分からない…」という方には、当サイト「TCマート」もぜひご覧いただきたいです。
私たちは、ただ機能的なだけでなく、着ていて心が弾むような、おしゃれなデザインの介護・シニア向け衣類を多数取り揃えています。TCマートは、機能性とデザイン性を兼ね備えたシニアファッションの総合サイトとして、幅広いアイテムをご提供しています。
例えば、着脱が簡単な前開きのポロシャツやブラウス、ウエストゴムで履き心地楽々なリラックスパンツなど、この記事でご紹介したポイントを押さえたアイテムがきっと見つかるはずです。
TCマートのシニアファッションはこちらから >>https://www.tcmart.jp/
すっきり片付く!衣類の収納アイデア
・ラベリング: 引き出しや衣装ケースに「夏物トップス」「冬物ズボン」など、ラベルを貼っておくと一目瞭然です。
・たたまない収納: シャツやズボンは、たたむよりハンガーにかける方がシワにならず、本人も選びやすくなります。
・引き出しの中の工夫: 仕切り板を使ったり、立てて収納したりすると、下の服が取り出しにくくなるのを防げます。
まとめ
高齢の親御さんとの同居に向けた服の準備は、一見大変に思えるかもしれません。しかし、一つひとつポイントを押さえて進めていけば、決して難しいことではありません。
大切なのは、
・安全で、着替えやすいこと
・洗濯がしやすく、清潔を保てること
・そして何より、ご本人の「好き」という気持ちを尊重すること
この3つです。
今回ご紹介した選び方や準備リストを参考に、親御さんが毎日を快適に、そして笑顔で過ごせるような一着を見つけてあげてください。親御さんにぴったりの服を選ぶことは、これからの新しい生活を応援する、あなたからの素敵な贈り物になります。
もし、着替えやすい介護用の衣類やおしゃれなシニアファッションをお探しでしたら、私たち「TCマート」が全力でサポートさせていただきます。ぜひ一度、サイトを覗いてみてくださいね。



















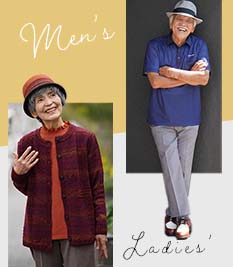

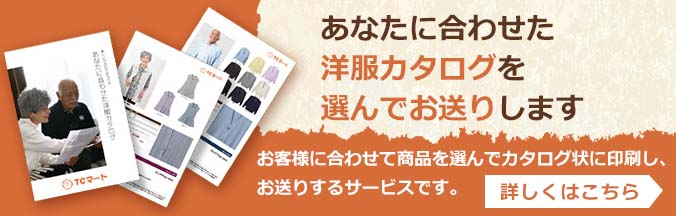
 乾燥機対応 婦人 鹿の子 選べる長袖ポロシャツ&全開ポロシャツ
乾燥機対応 婦人 鹿の子 選べる長袖ポロシャツ&全開ポロシャツ 日本製 婦人 ラグラン長袖 前開きポロシャツ
日本製 婦人 ラグラン長袖 前開きポロシャツ 乾燥機対応 婦人 鹿の子 選べる七分袖ポロシャツ&全開ポロシャツ
乾燥機対応 婦人 鹿の子 選べる七分袖ポロシャツ&全開ポロシャツ 乾燥機対応 婦人 鹿の子 花柄プリント 全開ポロシャツ
乾燥機対応 婦人 鹿の子 花柄プリント 全開ポロシャツ 乾燥機対応 花柄プリント さらさら ミニハイネック カットソー
乾燥機対応 花柄プリント さらさら ミニハイネック カットソー 日本製 楊柳ストレッチ 七分袖 プリントカットソー
日本製 楊柳ストレッチ 七分袖 プリントカットソー 乾燥機対応 さらさら丸首ギャザー後ろ長めカットソー
乾燥機対応 さらさら丸首ギャザー後ろ長めカットソー 乾燥機対応 鹿の子 カーディガン
乾燥機対応 鹿の子 カーディガン 乾燥機対応 あったか起毛 スッキリ切替 後ろ長め 丸首カットソー
乾燥機対応 あったか起毛 スッキリ切替 後ろ長め 丸首カットソー 乾燥機対応 春秋用 ストレッチチノパンツ 股下55cm
乾燥機対応 春秋用 ストレッチチノパンツ 股下55cm 乾燥機対応 春秋用 さらさらきれい見えパンツ 股下58cm
乾燥機対応 春秋用 さらさらきれい見えパンツ 股下58cm 乾燥機対応 鹿の子 ポケット付き ベスト
乾燥機対応 鹿の子 ポケット付き ベスト